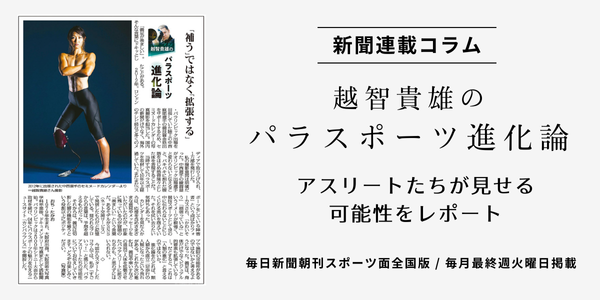義足をかっこよく履きこなす女性たちを撮影する

壁に気づく
2000年、シドニー・パラリンピックの撮影で見つけたものは、思いもよらない〝壁〟だった。僕自身がいつの間にか立てていた壁、それは障害者と括られる人達を「かわいそうな人」「がんばっている人」「支援が必要な人」という勝手な先入観で見てしまっていた壁だった。その壁を見つけ、同時にカメラのファインダー越しに見たアスリート達がその壁を壊してくれた。
パラリンピックは単なる「障害者のスポーツ」ではない。競技場で選手のパフォーマンスを目のあたりにすると、それまで自分が持っていた〝障害者〟という言葉のネガティブなイメージが、パッと消える。これは純粋に「競技スポーツ」なんだと、実感する。「障害者の」という無責任な先入観を、こちらが勝手に作って壁にしていたのだ。それを知り、壁を取り払うと、僕の世界が一挙に広がった。それはたぶん、僕だけではなく、世界が変わったことだと思う。
プロジェクトのきっかけ

2011年8月、撮影中のアクシデントでヘルニアによる間欠性跛行を患い、寝たきりの生活を数ヶ月間、余儀なくされた。たくさんの病院に通院したが、ほとんど回復の兆しが見えない。月日が過ぎ、写真の道を断念するつもりで、それまで撮影してきたパラリンピックの写真展を開催した。2012年10月のことで、これが集大成のつもりだった。ところがその写真展を知ったハッセルブラッド・ジャパン(スウェーデンのカメラ会社)から、撮影協力の申し出を受けることになる。
それならばと奮起したが、いざハッセルのカメラを手にすると、中判カメラなのでこれが重い。腰に激痛が走る。やはりムリかと諦めかけたが、周囲からの励ましを受けて、あらためて考えてみた。僕が本当にやりたいことは何だったのか──「壁を取っ払うこと」じゃなかったのか。今、その原点に戻ろう。その後、石川県の病院で入院生活をし、「治そうとする気持ち」が大事と病院で教えられ、回復の兆しがでてくる。
入院中、なにを撮影したいかと考えたとき、脳裏に浮かんだのが、義足をかっこよく履きこなすパラアスリートたちだった。長年、撮影取材し続けてきた中で、競技用義足を作る臼井二美男氏と出会った。彼の作る義足は、「もの」という領域をはるかに超えていた。ミニスカートやハイヒールが履ける義足やファッショナブルさを追求した義足、世界最高峰の競技スポーツであるパラリンピックに出場するアスリートの為の競技用義足と多岐にわたる。ユーザーのあらゆる要望に応え、どんな難しい義足作りにも挑戦してゆく姿には、感服する。彼の作った競技用義足から浮き立つ血管が、僕には見えたことがある。女性の美しく魅力的な義足に興奮しドキドキしたことがある。これらが鉄で作られたものとは到底信じられない。それは、愛に溢れ、美しく、力強く、そしてカッコいい。義足からその人の個性や魅力を強く感じるのだ。
退院後、僕は臼井氏を訪ねた。義足の人たちを撮りたいと相談すると、「義足を隠さなければいけないと考える人がいる」。「それならまず、臆せず隠さずにいる人を撮りましょう」「誇らかに見せている人を撮ろう」「見せる気概のある女性を」と、話が進む。『切断ヴィーナス』のプロジェクトがスタートした。
2013年3月から撮影を重ね、4月には写真展を開いた。幸いなことに、各メディアで好評を得て、海外からは展示の引き合いも来た。やがて、共感する人、サポートを申し出る人が次第に集まってくる。これはみなの力が大きな渦を作っていくぞ、そんな予感がした。
撮影と伝えたい事
撮影では、本人の個性が一番大事と考え、撮影前にヒアリング(取材)を重ね、本人を知ることからはじめた。当然のことながら、みな自分の世界観がある。被写体自らが衣装を選び、中にはスタイリストやヘアデザイナーを連れてくる人もいる。そこに、個性も、自信も、美しさも、被写体からの表現として現れてくる。
そんな彼女たちの表現した魅力を、一人でも多くの人に知ってもらいたい。そして写真を見た人がポジティブな行動を起こすきっかけになればと願っている。
どんな困難にめぐりあっても自分を信じて行動し続ければ、自分自身も周りも変えられると思う。写す真実と書いて、“写真”。これからも写真の力を信じて、被写体のそのままを撮り続けたい。